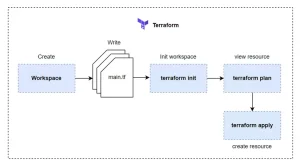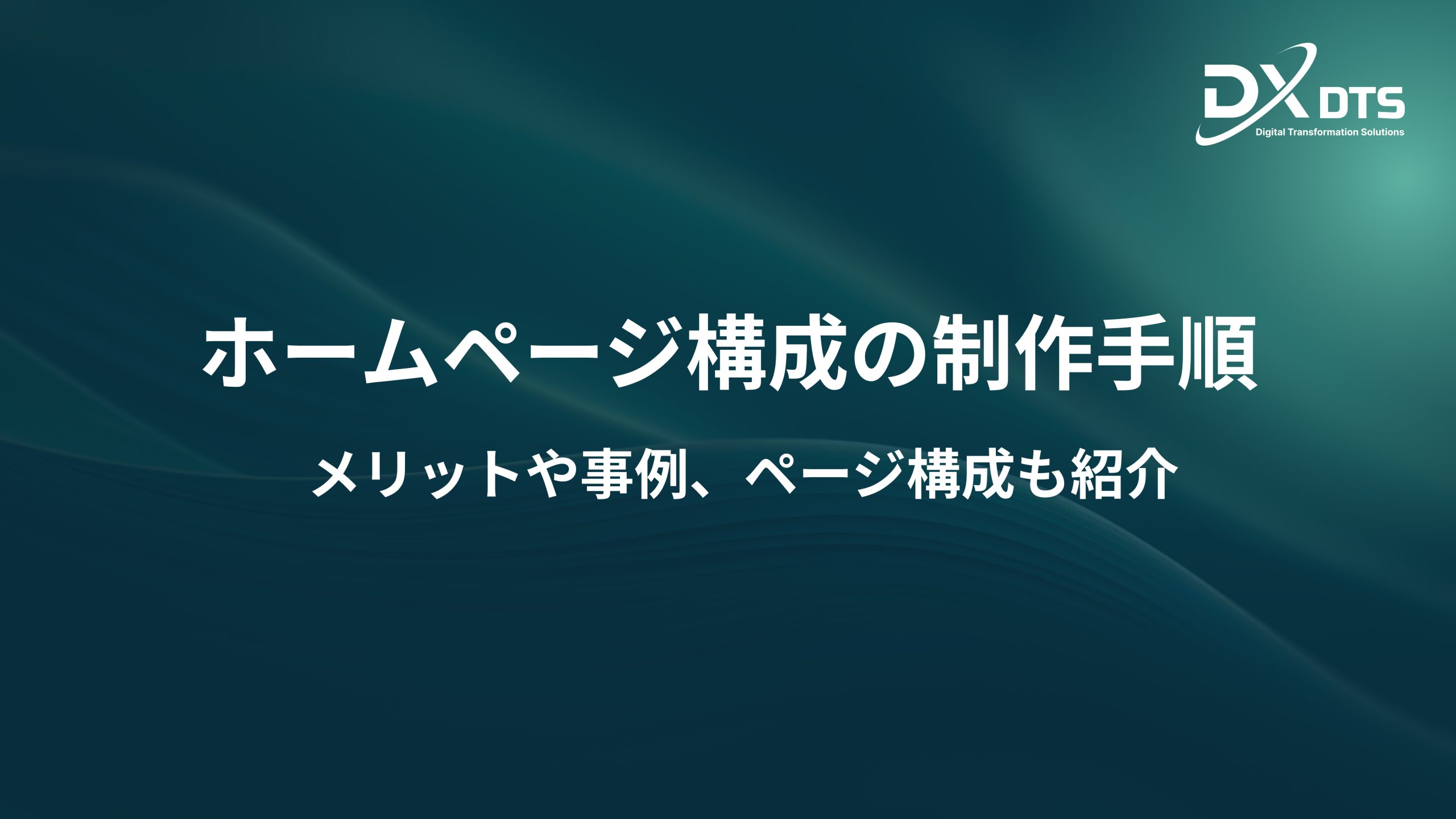
ホームページを作成する際に最も重要なのは、ユーザーがストレスなく目的の情報にたどり着けることです。使いやすさを重視した設計は、効果的なホームページづくりの基本と言えます。
そのためには、適切なホームページの構成が欠かせません。しかし、構成の作り方やポイントを理解していないと、的確な設計を行うのは難しいでしょう。
本記事では、ホームページの構成を作る手順や考え方を詳しく解説します。また、実際に活用できる構成図のダウンロードも可能ですので、ぜひ参考にしてください。
ホームページ制作ならDTSにお任せください
弊社DTSでは、ホームページの構成作成からサポートいたします。
コーポレートサイトやサービスサイトはもちろん、会員制サイトやECサイトの制作も対応可能です。まずは、お客様の理想のサイトについてお聞かせください。
Table of Contents
ホームページの構成の考え方
ホームページを作成する際は、事前に構成をしっかり設計し、それに沿って実装することが重要です。まずは、ホームページの構成について基礎から理解しておきましょう。
1. ホームページの構成とは
ホームページの構成とは、情報の配置や内容を視覚化した全体図のことです。情報を適切に整理し配置することで、ユーザーの動線を最適化し、目的のページへスムーズに誘導できます。
構成が不十分なホームページでは、ユーザーが必要な情報を見つけられず、離脱してしまう可能性が高くなります。そのため、実装前にユーザー視点で構成を設計することが重要です。
ホームページの構成には、大きくサイト全体の構成を示す「サイトマップ」と、各ページのレイアウトを決める「ワイヤーフレーム」の2種類があります。
2. ホームページのサイト構成(サイトマップ)
ホームページ全体の構成図は「サイトマップ」と呼ばれます。トップページを第1階層とし、そこからリンクでつながる下層ページを第2階層、さらにその下にある情報を第3階層と、階層構造を作成していきます。
類似するものにページの一覧表である「ディレクトリマップ」がありますが、サイトの階層を決める際には、階層構造を視覚化したマップを作成したほうが分かりやすくなります。
サイトマップの役割は、情報の整理と視覚化です。必要な情報を適切にカテゴライズすることで、ユーザーにとって分かりやすくなるだけでなく、作成側もサイト全体の構成を把握しやすくなります。
また、サイトマップには、ユーザー向けに構成を提示する「HTMLサイトマップ」と、検索エンジン向けに最適化された「XMLサイトマップ」の2種類があります。
3. ホームページのページ構成(ワイヤーフレーム)
各ページの構成は「ワイヤーフレーム」と呼ばれます。ワイヤーフレームは、ページ上の情報の配置を視覚化した設計図のようなもので、事前に作成することでページ全体のイメージを把握しやすくなります。また、制作会社と発注者でワイヤーフレームを共有することで、認識のズレを最小限に抑えられます。
ワイヤーフレームと似たものに「デザインカンプ」があります。デザインカンプは、ワイヤーフレームに加えて、ページごとの具体的なデザイン要素も盛り込まれたものです。
一方、ワイヤーフレームは情報の大まかな配置を示す「レイアウト設計」であり、この段階ではデザインの細かい要素まで考慮する必要はありません。
ホームページのサイト構成(サイトマップ)をつくるメリット
サイトマップを事前に作成することで、ホームページ全体の構成やイメージを明確に把握できます。情報を整理することで、ユーザーにとって使いやすいホームページの実現にもつながります。ここでは、サイトマップを作成するメリットについてご紹介します。
1. 必要なページの内容や数の把握
サイトマップを作成することで、必要なページの内容や数を明確に把握できます。サイトマップは、情報の関連性を整理しながら、掲載するページや配置、階層を決めることで完成します。カテゴリごとに情報を整理し、適切なページ構成を考えることで、必要なページ数や掲載内容が自然と決まってきます。
特にページ数が多いホームページでは、事前に構成を整理しないと、重複したページが発生する可能性があります。重複ページがあると、検索エンジンに「コピーコンテンツ」と判断され、評価が下がることで集客に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、ページ数が多くなるほど、サイトマップを活用して全体の構成を把握することが重要です。
2. 完成後のホームページをイメージできる
サイトマップを作成すると、完成後のホームページのイメージを明確に描くことができます。
ホームページ制作において最も重要なのは、「制作会社と発注者の間でイメージのズレがないこと」です。もし共有できていない状態で制作を進めると、完成後に「想像していたものと違う」といった問題が発生し、修正や再制作が必要になる可能性があります。 これには時間やコストがかかるため、事前にしっかりとイメージを共有しておくことが重要です。
サイトマップを活用すれば、構成や掲載する情報を具体的に共有でき、イメージのズレを防ぐことができます。 さらに、情報の不足やページの重複がないかも事前に確認し、スムーズな制作を進めることが可能になります。
3. 情報が探しやすいホームページが出来る
サイトマップを作成することで、ユーザーが情報を探しやすいホームページを構築できます。
1つのページに膨大な情報が詰め込まれていると、必要な情報を見つけるのが難しくなります。しかし、ページを適切に分割することで、ユーザーは目的の情報にスムーズにアクセスできます。
例えば、サービスの料金を知りたい場合、サービス内容・料金・特徴・機能・お客様の声などが1ページにまとめられていると、料金情報を探し出すのに手間がかかります。
しかし、サイトマップでホームページの全体構成を可視化することで、「サービス」という大カテゴリの中に「サービス内容」「料金」「特徴」などのページを設けるといった整理が可能になります。 これにより、ユーザーが目的のページにたどり着きやすくなります。
このように、情報を探しやすいサイトを設計することで、ユーザビリティを向上させ、使いやすいホームページを実現できます。
サイト構成の制作手順
ユーザーにとって使いやすいホームページを作るには、サイト構成が重要です。
しかし、適切な準備を怠ると、必要な情報が抜け落ちたり、分かりにくいサイトになってしまう可能性があります。
ここからは、効果的なサイト構成を作成するための手順をご紹介します。
1. 目的の明確化
サイト構成を考える際は、まずホームページの目的を明確にすることが重要です。
目的が曖昧なままでは、作成後の効果測定や改善が難しくなります。単にホームページを作ることが目的にならないよう、自社がホームページを通じて得たい成果を明確にしましょう。
例えば、ホームページの目的には以下のようなものがあります。
- 商品やサービスの販売・プロモーション
- お問い合わせ・資料請求の受付
- 企業のブランディング
- 採用活動
また、ターゲットを明確にすることも欠かせません。
ターゲットと目的をはっきりさせることで、ユーザーのサイト内での行動をイメージしやすくなり、より使いやすいサイト構成を設計できます。
2. 必要なページを書き出す
目的を明確にしたら、必要なページをリストアップしましょう。
ユーザーの目的を意識しながら、掲載すべき情報を洗い出します。この段階では、カテゴリー分けは考えずに、まずは必要な情報を漏れなく挙げることが大切です。
また、担当者だけの視点に偏らないよう、社内外の意見を参考にするのも効果的です。
場合によっては、同業他社のホームページをチェックしながら、どのような情報が必要かを検討するのもよいでしょう。
一般的なコーポレートサイトでは、以下のようなページが含まれます。
- トップページ
- 会社概要
- 代表挨拶
- 企業理念
- 沿革
- 事業・サービス内容
- 商品情報
- IR情報
- 最新情報
- 採用情報
- 導入事例・お客様の声
- お問い合わせフォーム
このように必要なページを洗い出しておくことで、サイト構成の設計がスムーズになります。
3. ページを分類する
次に、書き出したページを整理し、カテゴリごとに分類しましょう。
似た情報をグループ化することで、サイト全体の構成が明確になります。
例えば、先ほど挙げたコーポレートサイトの情報では、以下のように整理できます。
- 会社情報(会社概要 / 沿革 / 企業理念 / 代表挨拶)
- 事業・サービス(事業内容 / 商品情報)
- 企業活動(IR情報 / 最新情報)
- 採用情報(採用情報 / お客様の声 / 導入事例)
- お問い合わせ(お問い合わせフォーム)
分類の際には、他社のホームページを参考にすると整理しやすくなります。
ただし、情報によっては明確なカテゴリーに分けられない場合もあるため、無理にグループ化せず、単独ページとして扱うことも検討しましょう。
4. 階層を意識した構成図にする
最後に、カテゴライズした情報にトップページを加えて、サイトの構成図を作成します。
構成図を作成する際は、「階層構造」を意識することが重要です。
- 第1階層:トップページ
- 第2階層:トップページから1クリックでアクセスできるカテゴリページ(例:会社情報、事業内容、採用情報など)
- 第3階層:第2階層のページからさらに遷移する詳細ページ(例:企業理念、代表挨拶、商品詳細など)
このように、情報を階層ごとに整理することで、ユーザーが目的のページにスムーズにたどり着ける分かりやすいサイト構成を作ることができます。
ホームページのページ構成(ワイヤーフレーム)の考え方
これまでは、ホームページ全体のサイトマップについて説明しました。
しかし、ホームページを使いやすくするには、各ページの構成も分かりやすく設計することが重要です。
ここからは、ワイヤーフレームの考え方についてご紹介します。
1. どのページの構成を作るか
ワイヤーフレームを作成する際は、対象とするページを選定することが重要です。
ホームページには多くのページがあるため、すべてのページのワイヤーフレームを作成するのは大変な手間がかかります。そのため、キーとなるページに絞って作成し、類似するページはワイヤーフレームを流用すると効率的です。
キーとなるページとは、
- トップページ
- 目的達成に重要なページ(例:ECサイトなら商品ページ)
また、競合との差別化を図るページや、独自のコンテンツを持つページについても、ワイヤーフレームを作成しておくと、より明確な設計が可能になります。
2. デザインを作り過ぎない
ワイヤーフレームを作成する際は、デザインにこだわりすぎないことが重要です。
ワイヤーフレームの目的は、各ページのレイアウトを整理することであり、デザインを決めることではありません。デザインを細かく作り込んでしまうと、構成の本質が見えにくくなったり、制作の進行が遅れたりする可能性があります。
ワイヤーフレームでは、「どの情報をどの位置に配置すれば分かりやすいか」に重点を置き、シンプルに整理することを意識しましょう。
ページ構成やサイト構成を効果的にするために
サイトマップやワイヤーフレームを最大限に活用するには、いくつかの重要なポイントを押さえることが大切です。常にこれらのポイントを意識しながら構成を考えることで、より使いやすいホームページを設計できます。
ここからは、サイトマップとワイヤーフレームを効果的に活用するための方法をご紹介します。
1. 目的から構成を考える
ホームページの構成を考える際は、まず目的を明確にすることが重要です。目的を設定し、それを達成するための構成を設計していきます。想定ユーザーの行動を考えながら、ユーザーのニーズと自社の提供価値が一致するように調整しましょう。
特に大切なのは、「目的を1つに絞ること」です。ポータルサイトのように幅広いユーザー層を想定する場合もありますが、一般的なコーポレートサイトでは、複数の目的を持たせると方向性が曖昧になり、分かりにくいホームページになってしまいます。
目的が明確であれば、必要な情報やサイト内でのユーザーの動きも整理しやすくなり、結果として使いやすいサイトが完成します。もし複数の目的を設定する必要がある場合は、それぞれの目的に応じた個別のホームページを作成するのが理想的です。
2. 重要なページを明確にする
サイト構成を考えるうえで、重要なページを明確にすることも欠かせません。重要なページを中心に構成を設計することで、ホームページの目的をより達成しやすくなります。
ここでいう**重要なページとは、「目的を達成するために不可欠なページ」**です。例えば、リード獲得を目的とする場合、商品・サービス紹介ページや問い合わせフォームが最も重要なページとなります。
その他のページは、重要ページへと誘導する補助的な役割を担うものと考えましょう。ワイヤーフレームを作成する際も、重要度の高いページを基準に設計すると、より効果的な構成が作れます。
また、ホームページをリニューアルする際も、まずは重要なページから見直すことで、目的の達成率を最大化できます。
3. サイト構成は階層を深くしすぎない
サイト全体の構成を考える際は、階層を深くしすぎないことが重要です。階層構造を意識するのは大切ですが、深くしすぎるとユーザーが求める情報を探しにくくなったり、検索結果に表示されにくくなったりする可能性があります。理想的な階層の深さは第3階層までとされています。
もし階層が深くなりそうな場合は、カテゴリを再編成する、または似た内容のページに情報をまとめるといった工夫をしましょう。
階層構造の例
- 第1階層:トップページ
- 第2階層:企業情報・サービス・お知らせ一覧
- 第3階層:企業概要・サービスA・お知らせ詳細
このように整理することで、ユーザーがスムーズに目的の情報へたどり着けるサイトを作れます。
まとめ
ホームページの構成を考える際は、目的やターゲットを意識し、使いやすさを重視することが重要です。ユーザビリティを向上させることで、結果的に自社の目的達成へとつながります。常にユーザー視点を意識した構成作りを心がけましょう。